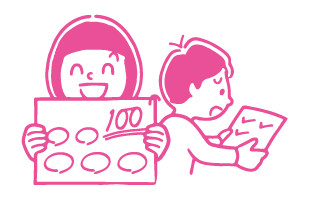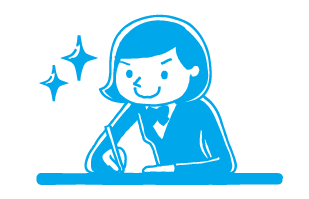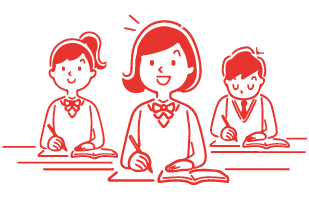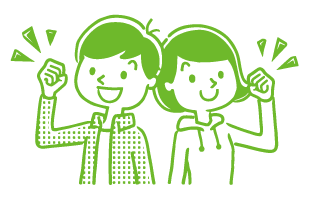塾長ブログ
【秀鍵ゼミナール塾長ブログ】その『知ってる』は、本当に『知っている』か?東大理三の英語を『再定義』する理由。

【秀鍵ゼミナール塾長ブログ】その『知ってる』は、本当に『知っている』か?東大理三の英語を『再定義』する理由。
どうも、秀鍵ゼミナールのだなそ~塾長です。
いきなりだが、君に問いたい。
「英単語を覚える」とは、どういう状態を指すのか?
多くの生徒は、そしておそらくは多くの塾の先生でさえ、「英単語帳の右側の日本語訳を言えること」だと答えるだろう。apple なら「りんご」、important なら「重要な」。それで一丁上がり。赤シートで隠して、言えたら次の単語へ。
本当に、それでいいのか?
その程度の「学習」で、人類の叡智が凝縮された論文を読み解き、世界最先端の研究者たちと渡り合う未来が、果たして拓けるのだろうか。
断言する。
そんなものは「学習」とは呼ばない。単なる「記号の暗記作業」だ。
東大理三を目指す、あるいはそれに準ずる最高峰の知性を目指す君たちが、そんな低次元の作業に貴重な時間を費やしているとしたら、それは罪だ。才能の無駄遣い以外の何物でもない。
うち、秀鍵ゼミナールの英語授業が「他塾の追随を許さない」と断言できるのは、この「単語一つ」に対する解像度、執着、そして深さが、根源的に違うからだ。
Case Study 1:単語の学習 ― “consider” を本当に「知る」ということ
例えば、consider という単語。
君たちの単語帳には、おそらく「~をよく考える」「~を考慮する」と書いてあるだろう。
まあ、間違いではない。中学レベルなら100点だ。
だが、秀鍵ゼミナールの授業はここから始まる。
第一階層:構文レベルの理解consider O (as) C の形を知っているか?「OをCとみなす、考える」だ。All things considered という慣用句は?「すべてのことを考慮に入れると」。take ~ into consideration は?「~を考慮に入れる」。
これらはセットだ。一つの単語から派生する「使い方」のバリエーション。ここまでやって、ようやく「受験生の入り口」だ。
第二階層:語源レベルの深掘りconsider は、con-(共に)と sider(星、ラテン語の sidus)から成る。
つまり、元々の意味は「星々を共に見つめる、観察する」こと。古代ローマの占星術師が、星の配置をじっくりと見て吉凶を占った様が、この単語の核なのだ。
このイメージを持つと、何が変わるか。
単に「考える」のではなく、「複数の要素(星々)を注意深く、全体的に、時間をかけて観察し、そこから結論を導き出す」という、重厚で知的なニュアンスが見えてこないか?
東大の入試で出てくる英文は、筆者が千思万考の末に選び抜いた言葉で書かれている。筆者が think ではなく consider を使った時、そこには「星々を眺めるような深い思索」の意図が込められているのだ。この感覚が、速読と精読を両立させる上で、決定的な差を生む。
我々の単語学習は、一つ一つがこのレベルだ。
語源を遡り、単語が持つ「本来の絵」を心に焼き付け、そこから派生する構文やイディオムを一つのネットワークとして脳内に構築する。
単語帳の1000語を「記号」として覚えた生徒と、1000の「世界」を脳内に構築した生徒。3年後、どちらが東大理三の合格通知を手にしているかは、火を見るより明らかだろう。
Case Study 2:文法の学習 ― それは「ルール」ではなく「OS」だ
次に文法。
多くの塾では、文法を「ルールブック」として教える。
「仮定法過去は、If S 過去形, S would V原形…はい、覚えなさい」
「関係代名詞の主格は、先行詞が人で…はい、次」
馬鹿げている。
英語の文法は、単なる暗記事項の羅列ではない。
それは、英語という言語を動かすための「オペレーティングシステム(OS)」そのものなのだ。
例えば、多くの受験生を悩ませる「カンマ付きの関係代名詞(非制限用法)」。My brother who lives in Tokyo is a doctor.My brother, who lives in Tokyo, is a doctor.
「カンマがあるかないかだけだろ?」と思った君、その時点で思考が浅い。
上の文は、「東京に住んでいる兄が」医者だという意味。話者には他にも兄がいて(例えば大阪に住む兄は弁護士、とか)、その中の「東京在住の」と限定している。情報の絞り込み(制限)だ。
下の文は、「私の兄は」医者です、という意味。兄は一人しかいない。その兄についての補足情報(追加)として、「(ちなみに)東京に住んでいるんだけどね」と付け加えているだけだ。
この違いが、なぜ重要か?
科学論文や評論文では、筆者がどの情報を「本質的」と捉え、どの情報を「補足的」と考えているかが、論理構造を把握する上で生命線となるからだ。
一つのカンマの有無が、筆者の思考のヒエラルキーを示している。それを読み取れずして、どうして「筆者の主張を400字で要約せよ」などという難問に太刀打ちできるというのか。
秀鍵ゼミナールの文法授業は、こうした「なぜ、その文法が存在するのか?」「ネイティブスピーカーは、何を表現したくてこの形を使っているのか?」という思想的背景にまで踏み込む。
仮定法がなぜ「現実からの距離感」を表現する装置なのか。現在完了形がなぜ「過去と現在の断絶を拒否する」時制なのか。
文法を「OSの設計思想」から理解すれば、無味乾燥な暗記は必要なくなる。すべてが論理的で、美しいシステムとして見えてくる。その時、君の脳内で英語は「第二のOS」としてインストールされ、ネイティブに近い感覚で文章を処理できるようになるのだ。
秀鍵の授業は「道場」である
我々の授業は、心地よいBGMが流れるカフェテラスのような生易しいものではない。
真剣を突きつけ合う「道場」だ。
私が「この consider は、なぜ think ではない?」と問う。
生徒は、単語の核イメージ、文脈、筆者の意図、あらゆる角度から思考を巡らせ、自らの言葉で説明しようと試みる。冷や汗をかきながら、脳をフル回転させる。
その答えが浅ければ、私は容赦なく斬り込む。
「なぜ、その根拠はどこにある?」「その解釈だと、この一文と矛盾が生じないか?」
この知的な格闘を通じてのみ、言語に対する真の感覚は磨かれる。
単語と文法というバラバラだった知識が、この道場での応酬の中で有機的に結合し、英文を「解体」し「再構築」するための、鋭利な思考のメスへと昇華していく。
東大理三は、単に英語ができる人間を求めているのではない。
英語というツールを完璧に使いこなし、複雑な事象を論理的に分析し、未知の問題に対して創造的な解を見出せる人間を求めている。
我々が教えているのは、そのための「思考の型」であり、「知性のOS」なのだ。
もし君が、ただ「偏差値を上げたい」「なんとなくいい大学に行きたい」という程度の志なら、うちの門を叩かないでほしい。もっと楽で、もっと優しい塾がいくらでもあるだろう。
だが、もし君が、自らの知性の限界に挑戦し、言語の深淵を覗き、世界のトップランナーとなるための本物の「知の力」を渇望しているのなら。
秀鍵ゼミナールの扉は、常に開かれている。
君のその「知ってるつもり」を、根底から覆す準備はできているか?
いつでも、道場で待っている。